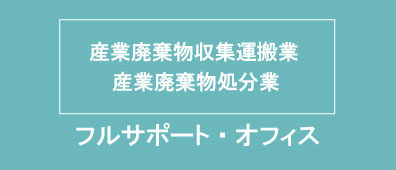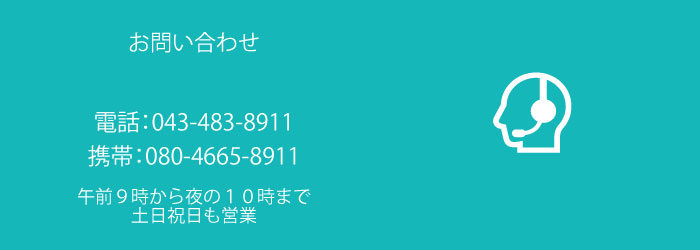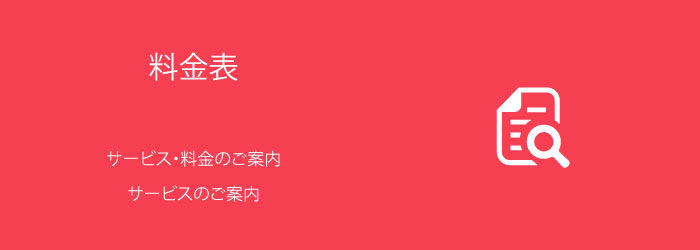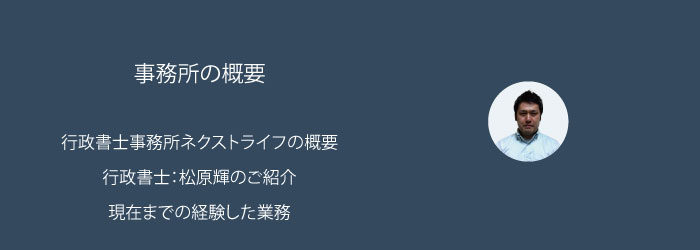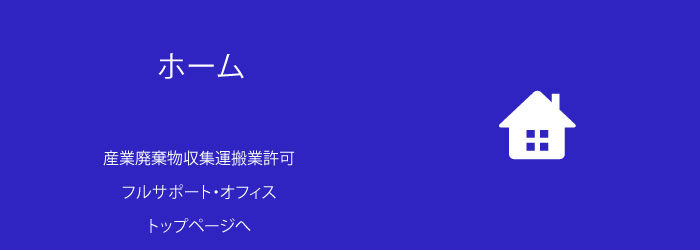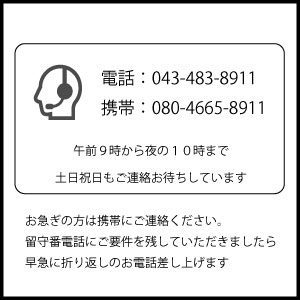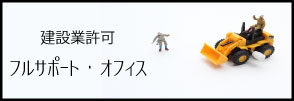廃棄物に該当しない場合とは
廃棄物は「ごみ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃液、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」と定義されていますが、
不要なものに該当しない場合は「廃棄物には該当しない」のでしょうか?
廃棄物に該当しないのであれば、例えば産業廃棄物と思っていたものが費用ではなく金銭的価値があり、それらを売買して収集運搬しているのであれば、廃棄物に該当しないのであれば「産業廃棄物収集運搬業許可」のある業者に依頼する必要もなくなる可能性だってあるわけです。
廃棄物該当性
「行政処分の指針について」(環廃産発第 1303299 号平成 25 年3月 29 日)について
産業廃棄物やその該当性について以下のように話されています。
また、これらを免れようとする不正がないよう以下のような判断基準があります。
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
【➁排出の状況】
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
【➂通常の取り扱い形態】
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
【➃取引価値の有無】
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
【➄占有者の意思】
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
そして廃棄物該当性の判断については、
規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されます。
各基準の実際の判断
【➀物の正常】
実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理が
なされていること等の確認が必要であること。
【➃取引価値の有無】
実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
【➄占有者の意思】
単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記➀から➃までの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断される。
総合的な判断が必要
以上の基準(総合判断説といわれる)をもって、廃棄物に該当するかしないかを判断するのが、
現在の主流です。貨幣的価値がある、と思っていても上記の上記➂にあるようにそもそも市場があるのか、➃にあるように複数のものに有償譲渡の実績があるか、等を考えたとき、判断が難しくなってきます。
まずは専門家・自治体への確認をしその上で活動をすべきです。